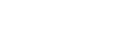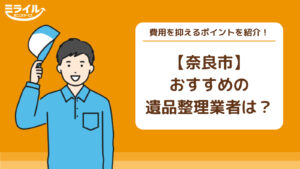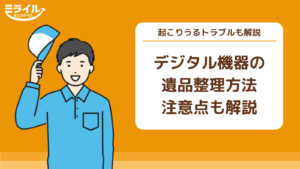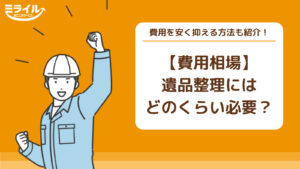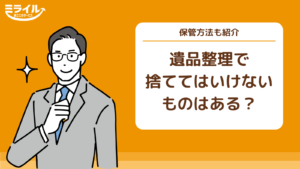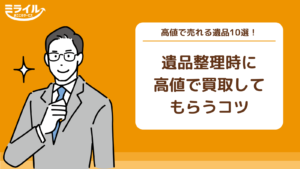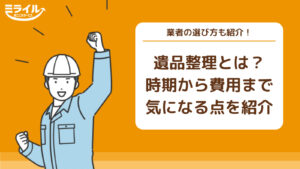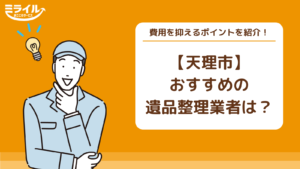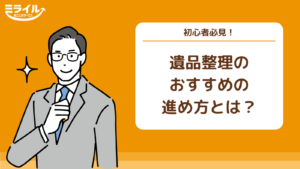ゴミ屋敷の遺品整理は自分でやる?それとも業者に頼む?プロが解説
遺品整理をしようとしたとき、部屋がゴミ屋敷のような状態になっていると「何から始めればいいのか分からない」「自分たちで片付けきれるのか不安」と感じる方は少なくありません。
ゴミの量や部屋の広さ、退去期限などの状況によっては、無理をして自力で進めようとするとかえって時間や労力を浪費してしまうこともあります。
この記事では、ゴミ屋敷の遺品整理を進めるための具体的な手順や必要な準備物、注意点を整理し、自力で対応できるケースと業者に依頼すべきケースの判断ポイントまで丁寧に解説します。後悔のない整理を行うために、まずは全体像を把握するところから始めましょう。
前提:ゴミ屋敷の遺品整理は日数・人数がかなり必要
ゴミ屋敷状態の住まいを遺品整理する場合、通常の片付けとは比べものにならないほどの時間と人手が必要です。
例えば、1K~1DKほどのゴミ屋敷であっても、作業スタッフ3〜5人で1〜2日はかかるのが一般的です。
間取りが広くなるにつれて必要な日数・人数も増加し、2LDK〜3LDK規模では6〜10人で3〜5日程度かかるケースもあります。
加えて、ゴミ屋敷では以下のような対応が発生するため、より作業が複雑になります。
- 生ごみや害虫など衛生リスクの高い廃棄物
- 埋もれた貴重品や遺品の仕分け
- 搬出時の階段・通路の養生や分別作業
- 場合によっては簡易的な消臭・清掃
さらに夏場は悪臭や害虫の影響が強まり、体力的な負担や安全対策の必要性も高まります。
このような理由から、ゴミ屋敷の遺品整理は「家族や知人だけで対応するには限界がある」と感じる方が多く、専門業者に依頼することで大幅な時間短縮と安全確保が可能になります。
ゴミ屋敷の遺品整理をする方法
ゴミ屋敷状態の遺品整理は、やみくもに始めると混乱しがちです。効率よく進めるには、事前の計画から処分・清掃までを段階的に進めることが重要です。
STEP1:ゴミ屋敷状態の部屋の片付けシミュレーションとスケジュールを立てる
ゴミ屋敷の遺品整理は、行き当たりばったりで始めてしまうと、どこから手をつけてよいかわからなくなりがちです。
まずは現状を把握し、片付けの段取りとスケジュールを立てることが大切です。
たとえば1DKの住まいで作業者が家族3人の場合、以下のような流れを想定すると効率的です。
| 日程 | 作業内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 1日目 | 玄関・通路の確保/ゴミの大まかな分別/害虫や腐敗物の処理 | まず動線の確保。安全かつ衛生的な状態を作る |
| 2日目 | キッチンやリビングの仕分け/遺品の選別/大きな家具の解体準備 | 貴重品や大事な書類を見落とさないよう丁寧に |
| 3日目 | ゴミの袋詰め・搬出/床や壁の簡易清掃/水回りの除菌 | 作業の仕上げとして部屋を整える |
このように、「どの部屋をいつ片付けるか」「何人で作業するか」を具体的に決めておくことで、無駄なく作業が進みます。
ゴミの量が多い場合や悪臭が強い場合は、体力的負担も大きくなるため、休憩をこまめに入れたり、日数に余裕を持たせたりすることもポイントです。
家族だけで作業する場合でも、事前に流れを可視化しておくことで、精神的な負担もぐっと軽くなります。
STEP2:遺品整理・ゴミ屋敷片付けに必要なものを用意する
ゴミ屋敷の遺品整理を自分たちで行う場合、事前に必要な道具をしっかり準備しておくことが成功のカギです。
現場ではゴミの量が多いだけでなく、悪臭やカビ、虫の発生などにも対処しなければならないことが多いため、安全性と効率を重視した備えが欠かせません。
以下に主な準備物をまとめます。
| 分類 | 必要なもの | 用途・注意点 |
|---|---|---|
| 衛生・防護用品 | マスク(できれば防臭タイプ) ゴム手袋・軍手 ゴーグル 防護服やエプロン | カビ・ホコリ・虫・腐敗物などから体を守る。臭いが強い場合は活性炭入りマスクが有効 |
| 清掃道具 | ほうき・ちりとり 掃除機(フィルター交換できるタイプ) バケツ・雑巾 消毒用アルコール・漂白剤 | 最後の掃除まで考えて用意。水回りや床の清掃に |
| 仕分け・搬出用 | ゴミ袋(可燃・不燃・資源ごと) ガムテープ・マジックペン 段ボール 台車・手押し車 | ゴミ分別や搬出の際に必要。種類ごとに袋を分け、外側に内容を記載しておくと後が楽 |
| その他便利グッズ | LEDライト(暗所対応) 大きめのブルーシート 小型工具(ドライバー・カッター等) | 作業中に停電や照明がない部屋も想定。養生や家具の解体用にも役立つ |
特に夏場は熱中症対策として飲み物・着替え・タオル類も必須です。
また、長靴や滑り止め付きの靴も安全確保のために準備しておきましょう。
大量のゴミを前にすると、精神的にも肉体的にも疲れやすくなります。
準備を万全に整え、「なるべく少ない手間で最大の成果が出せるように工夫すること」が、継続して作業を進めるコツです。
STEP3:ゴミ屋敷の遺品整理に着手する
準備が整ったら、いよいよ実際の片付け作業に入ります。
ゴミ屋敷の整理では、目に見えるものすべてが不要品に見えてしまいがちですが、本来捨ててはいけない大切な遺品や貴重品が埋もれていることも珍しくありません。
そのため、作業の初期段階では「捨てる前に確認する癖をつける」ことが重要です。
以下に、捨ててはいけないもの・価値がある可能性のある遺品の例を一覧で紹介します。
| 種類 | 具体例 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 貴重品 | 通帳・印鑑・現金・保険証券・証書類 | 再発行が面倒または不可。相続手続きにも必須 |
| 身分証明書・重要書類 | 免許証・マイナンバーカード・年金手帳・契約書 | 悪用や個人情報流出のリスクあり。慎重に扱う |
| 想い出の品 | 写真・手紙・日記・年賀状 | 故人とのつながりを感じられる大切な記録。すぐに判断せず一時保管がおすすめ |
| 高価なもの | 時計・宝石・カメラ・ブランド品・骨董品 | 外見上は汚れていても、専門業者では高値がつく可能性もあり |
| 相続・不動産関係 | 土地の権利書・登記簿・固定資産税の通知書 | 相続時に必須となるケースが多く、再取得に時間がかかる |
作業時は、「これは本当に捨てていいものか?」を確認する余裕が必要です。
もし迷った場合は、一時的に“保留ボックス”や“貴重品専用段ボール”などを設けておくと後から見直しやすくなります。
なお、故人の趣味のコレクションや手紙など、金銭的価値がなくても精神的価値が高いものは、一緒に作業する家族と相談しながら判断するのがベストです。
STEP4. ゴミを処分する
ゴミ屋敷の片付けで最も大変なのが、大量に出たゴミの処分です。
ゴミの量が多いと混乱しがちですが、地域のルールに従って正しく分別し、計画的に処分することが重要です。
大阪府内(例:大阪市)では、家庭から出るゴミは以下のように分類され、それぞれ異なる方法で処分する必要があります。
| 種類 | 処分方法 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 指定ごみ袋に入れて、週2回程度の回収日に出す | 生ごみ、衣類、紙くず、汚れのあるプラスチック類など |
| 不燃ごみ | 月1回程度の回収日に出す | 金属製品、ガラス、陶器、小型家電など |
| 資源ごみ | 曜日指定で分別収集 | ペットボトル、空き缶、ビン、新聞、ダンボールなど。きれいに洗ってから出す |
| 粗大ごみ | 事前予約制。電話またはインターネットで申し込みが必要 | 家具、布団など。粗大ごみ処理券の購入が必要。指定日に玄関先などに出す |
| 家電リサイクル対象品 | 購入店または指定引取場所への持ち込み | テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど。リサイクル料金と運搬費がかかる |
分別に迷ったときは、大阪市の「ごみ分別辞典」や環境局のホームページを参照するのが確実です。
また、ゴミの量が非常に多い場合、地域のルール上、一度に出せる量には制限があるため、数回に分けて出すか、清掃工場へ直接持ち込む方法も検討しましょう(事前確認が必要です)。
なお、古紙類や衣類はスーパーのリサイクルボックスや自治体の資源回収ステーションで受け付けている場合もあります。
手間はかかりますが、正しい分別・処分を行うことで、近隣トラブルや回収拒否といった二次的な問題を防ぐことができます。
迷ったときの対処法
- 金属が使われている小物類は「不燃ごみ」に分類
- プラスチック製品は汚れの有無で「資源ごみ」か「可燃ごみ」に分かれる
- 割れるもの、燃えないものは原則「不燃ごみ」
- 家電の処分は型番や製造年により対応が異なるため、自治体サイトやリサイクルショップで確認する
STEP5:床や壁、水回りなどの清掃を行う
ゴミの撤去が終わったら、最後に行うのが清掃作業です。
ゴミ屋敷状態が長期間続いていた場合、床や壁、キッチン・トイレ・浴室などの水回りには、汚れや臭い、カビの発生が見られることが多く、見た目以上に状態が悪化していることもあります。
以下のような箇所を重点的に掃除しましょう。
| 清掃箇所 | 主な作業内容 | 使用する道具・洗剤など |
|---|---|---|
| 床全体 | ほこり・汚れの除去、拭き掃除、場合によってはワックスがけ | 掃除機、モップ、アルカリ性クリーナー、雑巾 |
| 壁・天井 | クモの巣、ヤニ汚れ、カビの除去 | ハンディモップ、中性洗剤、除菌スプレー |
| キッチン | シンクの水垢・カビ・油汚れ除去、排水口の洗浄 | 重曹、クエン酸、スポンジ、排水口用ブラシ |
| トイレ | 黒ずみ・尿石の除去、換気扇の掃除 | 酸性洗剤、トイレ用ブラシ、手袋 |
| 浴室 | カビ・ぬめり・水垢の除去、排水口の掃除 | カビ取り剤、防カビ燻煙剤、ブラシ、ゴム手袋 |
特に水回りは衛生面の影響が大きく、放置すると悪臭や害虫の原因になるため、念入りな清掃が必要です。
また、壁紙や床材に染み込んだ臭いは、拭き掃除だけでは取れない場合もあり、その場合は重曹や消臭剤、換気の徹底を併用すると効果的です。
清掃が終わると、空間が一気に明るくなり、気持ちの整理もつきやすくなります。
作業の最後のステップとして、部屋の中を「住める状態に戻す」意識で丁寧に仕上げることを意識しましょう。
ゴミ屋敷の遺品整理を行う場合のスケジュール目安
ゴミ屋敷の遺品整理には、物件の広さやゴミの量に応じた作業期間が必要です。
ここでは、作業人数ごとのスケジュールの目安をご紹介します。
1LDKの場合
1LDK程度の間取りであっても、ゴミの量が多ければ2〜3日程度はかかると考えておくべきです。
玄関・リビング・キッチン・水回りなど作業範囲は広く、3人で1日6〜7時間の作業を2日間、汚れがひどい場合は3日目を予備日として見込むと安心です。
| 作業人数 | 想定日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2名 | 3〜4日 | 作業負担が重く、片付け・搬出に時間がかかる |
| 3〜4名 | 2〜3日 | 通路確保→仕分け→搬出→清掃の流れがスムーズに進行 |
スケジュール例
| 日程 | 作業内容 |
|---|---|
| 1日目 | 玄関・通路の確保、ゴミの分別、キッチン回りの仕分け |
| 2日目 | リビング・寝室の遺品整理、粗大ゴミの搬出準備 |
| 3日目 | 水回りの清掃、全体の仕上げ、残置物の確認 |
2LDKの場合
2LDKのゴミ屋敷は、部屋数が増えることで遺品の量も大幅に増加します。
家族3〜4人で対応する場合、少なくとも3〜5日は確保しておいた方が良いでしょう。
1日では終わらないため、計画的に部屋ごとに作業を分けることが重要です。
| 作業人数 | 想定日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 3名 | 4〜5日 | 作業が長引くと体力面でも負担が大きくなる |
| 4〜5名 | 3〜4日 | 分担して進めることで時間短縮が可能 |
スケジュール例
| 日程 | 作業内容 |
|---|---|
| 1日目 | 通路確保、キッチン・ダイニングの仕分け |
| 2日目 | 寝室1、クローゼット内の整理、ゴミの袋詰め |
| 3日目 | 寝室2、リビング、貴重品や写真類の選別 |
| 4日目 | 粗大ごみの搬出、水回り・床の清掃、最終確認 |
3LDK以上・1軒家の場合
3LDK以上の広い家や一戸建ての場合は、作業量も負担も格段に増します。
長年手つかずだった家屋では、2階・納戸・屋根裏・倉庫などにも遺品やゴミがあるケースが多く、1週間以上かかることも想定しておく必要があります。
| 作業人数 | 想定日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 3〜4名 | 6〜8日以上 | 屋外の整理や搬出ルートの確保にも時間がかかる |
| 5〜6名 | 4〜6日程度 | 部屋ごとの分担で効率化可能だが体力的負担は大きい |
スケジュール例
| 日程 | 作業内容 |
|---|---|
| 1日目 | 通路・玄関・階段まわりの確保、ゴミの分別開始 |
| 2日目 | キッチン、1階リビングの遺品・ゴミ仕分け |
| 3日目 | 1階寝室・和室などの整理、クローゼット・押し入れの確認 |
| 4日目 | 2階各部屋の仕分け、納戸や屋根裏のチェック |
| 5日目 | 粗大ごみ・家電の搬出、家の外まわり(ベランダ・物置など)の清掃 |
| 6日目 | 水回りの清掃、消臭・拭き掃除、最終確認・残置品処分判断 |
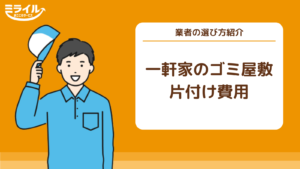
この場合自分でやる?業者に頼む?遺品整理の依頼の判断ポイント
遺品整理は自分でできるケースもあれば、業者に依頼した方がよい場合もあります。
ここでは、判断の目安となるポイントを紹介します。
1. ゴミ屋敷の度合いで決める
片付けの難易度は、部屋の状態で大きく変わります。
たとえば「床が見える・踏める」状態なら自力でも進められる可能性がありますが、「床が見えない」「天井近くまでゴミが積みあがっている」「悪臭や虫が発生している」場合は、作業自体が困難であるため、業者に依頼するのが現実的です。
| 状態 | 自力対応の可否 |
|---|---|
| 床が踏める・生活動線が確保できる | 自力でも可能性あり |
| 通路が完全に塞がっている | 要業者対応 |
| 強い臭い・害虫・腐敗物あり | 衛生上、業者推奨 |
| 天井近くまで積み上がっている | 自力では物理的に困難 |
2. 広さで決める
間取りが広くなるほど、単純に作業量が増えるため、対応可能な範囲かどうかを事前に見極める必要があります。
1Kや1DK程度であれば自分たちでの対応も検討可能ですが、2LDK以上、特に一戸建てになると家全体に遺品やゴミが広がっているケースが多く、時間も体力も必要です。
| 間取り | 自力対応の可否 |
|---|---|
| 1K〜1DK程度 | 家族で対応可能な範囲 |
| 2LDK〜3LDK | 作業人数と時間が確保できれば可能だが厳しめ |
| 3LDK以上・一戸建て | 多くの場合、業者の力を借りた方が現実的 |
3.実施できる人数で決める
作業にあたる人数が限られている場合、自力では日数がかかりすぎるリスクがあります。
特に高齢者や体力に不安のある方のみで対応する場合は、無理に進めるより業者に依頼した方が安全です。
| 人数 | 自力対応の目安 |
|---|---|
| 3人以上で平日数日確保できる | 1〜2部屋程度なら可能性あり |
| 1〜2人しか確保できない | 重度の片付けには向かない/業者推奨 |
| 高齢の家族のみ | 事故・けがのリスクを避けるため業者に依頼を検討 |
4.予算で決める
予算に限りがある場合、可能な範囲で自分たちで行い、処分や搬出だけを業者に頼むといった部分的依頼も選択肢です。
ただし、自力での作業が長引けば精神的・身体的な負担や追加コストがかかることもあるため、「安く済ませたい」だけで判断せず、費用対効果を冷静に見極めることが大切です。
| 予算状況 | 対応方針の一例 |
|---|---|
| できるだけ安く済ませたい | 分別・袋詰めは自力、搬出のみ業者など部分依頼を検討 |
| 数万円〜十数万円の予算がある | 1部屋〜2部屋程度の業者依頼も可能 |
| 時間や体力に不安がある+予算に余裕あり | 一括依頼でストレスや事故のリスクを回避できる |
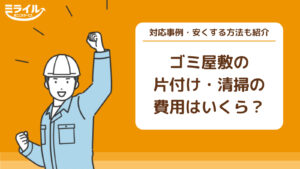
5.退去期限で決める
遺品整理を急ぐ理由の一つが賃貸住宅などの退去期限です。
「○日までに明け渡し」「管理会社から早急な撤去を求められている」といった状況では、自力で片付けようとして間に合わず、結果的に違約金や追加家賃が発生するリスクもあります。
限られた期間内で片付けるには、日数×作業人数を逆算し、「間に合わない可能性が高い」と判断した時点で業者に依頼することが賢明です。
| 状況 | 対応方針 |
|---|---|
| 退去まで1週間以上ある+人数を確保できる | 計画的に自力で進めることも可能 |
| 退去まで数日しかない/一人で作業する | 時間的に間に合わない可能性が高く、業者依頼が安全 |
| 管理会社から催促を受けている | トラブル回避のため即時対応が必要。業者推奨 |
退去期限に遅れると、敷金の返還がなくなるだけでなく、別途清掃費や損害請求が発生する場合もあります。
時間に余裕がない場合は、自力で進められる範囲を見極めつつ、要所はプロの力を借りる判断も視野に入れましょう。
ゴミ屋敷を遺品整理する際に注意しなければいけないポイント
ゴミ屋敷の遺品整理では、想定外のトラブルが起きやすいため注意が必要です。
ここでは、事前に知っておきたい代表的な注意点を紹介します。
捨ててはいけない物を事前に把握しておく
ゴミ屋敷の中でも、遺品の中には貴重品や重要書類、大切な思い出の品が混在している可能性があります。作業を効率よく進めたいからといって、すべてを一括で廃棄してしまうのは危険です。
通帳や印鑑、契約書類、写真や手紙などは、事前に「残すものリスト」や一時保管用の箱を用意し、仕分けしながら進めることが大切です。
自治体のゴミ処理ルールを把握しておく
大量のゴミを出す際は、地域の分別ルールや回収日、粗大ごみの申込み方法を事前に確認しておくことが必須です。
とくに大阪市など都市部では、一度に出せる量に制限がある・予約制の粗大ごみがあるなど細かいルールがあります。分別ミスや違反行為は、収集拒否や近隣からの苦情につながるリスクもあるため注意しましょう。
無理なスケジュールを立てない
「一気に終わらせたい」と焦る気持ちはわかりますが、無理なスケジュールで進めると途中で力尽きてしまったり、雑な作業になってしまう恐れがあります。
現場の状況や作業人数に応じて、余裕をもった日数を設定することが成功の鍵です。特にゴミ屋敷の場合は、初日の想定が甘いとその後すべてがずれ込むこともあるため、慎重に見積もりましょう。
害虫・カビ・有害物質への対策をしておく
ゴミ屋敷では、長期間蓄積した生ごみや湿気の影響で、害虫・カビ・悪臭・動物のフンなどが発生しているケースも多く見られます。
そのまま作業に取りかかると、健康被害(アレルギー・感染症)を引き起こすリスクもあるため、防塵マスク・ゴム手袋・長袖・換気など、万全の装備で臨む必要があります。
体力・精神面への負担を甘く見ない
片付けは肉体労働であると同時に、精神的にも負荷がかかる作業です。故人の持ち物を目の前にしながら、長時間の清掃・搬出を行うのは予想以上に消耗します。
作業は午前・午後に分けて区切る、こまめに水分補給と休憩を入れるなど、無理のない進行を心がけましょう。
周囲(近隣住民など)への配慮を忘れない
大量のゴミの搬出や清掃作業では、騒音・ニオイ・車の出入りなどで近隣に迷惑をかけてしまうこともあります。
作業前に一言声をかけておいたり、通路をふさがないよう注意するなど、周囲への気遣いを忘れないことが大切です。
また、複数人で作業を行う場合は、親族間で意見が割れることもあるため、事前にルールを決めておくとスムーズです。
貴重品・重要書類は一時保管箱にまとめておく
通帳・保険証券・遺言書・印鑑などの貴重品は、ゴミと一緒に混在していることが多く、誤って捨ててしまいやすいものです。
片付け作業を始める前に、「これは大事かもしれない」と思うものをとりあえず保留できる専用箱(段ボールなど)を用意しておくことで、あとから見直すことができ、後悔を防げます。
ゴミ屋敷の遺品整理ならミライルまごころサービスへお任せください
ゴミ屋敷状態のお部屋を遺品整理するのは、体力的・精神的な負担が大きく、時間や知識も必要とされる作業です。
「どこから手をつけていいかわからない」「作業が進まないまま期限が迫っている」
そんなお悩みがある場合は、無理せず、専門のプロに相談することが解決への近道です。
ミライルの「まごころサービス」では、遺品整理士が在籍し、状況に応じた柔軟な対応と丁寧な作業を心がけています。
関西・名古屋エリアに特化し、地域密着型でご相談から作業完了まで責任を持ってサポートいたします。
- 現地調査・お見積もり無料
- ご家族の想いを大切にした仕分け対応
- 急なスケジュールにも可能な限り対応
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
一歩踏み出すだけで、気持ちも空間も、きっと大きく変わります。